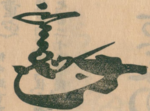検索結果
このウィキでページ「輿田村」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 田村麻呂は大納言に昇進しており、子の坂上広野も近江国の関を封鎖するために派遣されている。 嵯峨天皇側の動きを知った平城上皇は激怒して9月11日(810年10月12日)早朝、挙兵することを決断し、薬子と共に輿に乗って平城京を発し、東国へと向かった。嵯峨天皇は田村…92キロバイト (13,535 語) - 2024年5月8日 (水) 16:02
- 坂上 田村丸(さかのうえ の たむらまる)は、田村語り並びに坂上田村麻呂伝説に登場する伝説上の人物。坂上 田村麻呂(さかのうえ の たむらまろ)とも。 平安時代の征夷大将軍としても高名な大納言の坂上田村麻呂は歴史的事実とはかけ離れた説話・軍記物語・寺社の縁起などに頻繁に登場したことで、その人物像も次…45キロバイト (7,666 語) - 2024年1月10日 (水) 03:38
- 坂家宝剣 (カテゴリ 坂上田村麻呂)では「式部卿・敦実親王の剣を持っていたが、白河上皇からお召しがあって献上した。今は鳥羽の宝蔵に伝来しているだろう。この剣は醍醐天皇が野行幸のときに腰輿の御剣として持ち出され、石突がなくなったが、岡の上にて「皇室伝来の剣であるのに」と嘆いていると、野行幸に同行する狩猟の犬が石突をくわえてきて元に戻っ…16キロバイト (2,668 語) - 2024年3月7日 (木) 08:36
- 天正7年(1579年)10月、仙道の三春城主・田村清顕より婚儀の相談があり、御入輿の日取り、路次警固等合い調う。その冬、政宗が13歳のとき、清顕の娘、当時11歳の愛姫(めごひめ)(伊達政宗と同じく伊達稙宗を曽祖父にもつ)を正室に迎える。伊達郡梁川城で輿の引継ぎが行われ、伊達成実・遠藤基信らに守られ…98キロバイト (15,869 語) - 2024年6月7日 (金) 04:14
- 悪路王 (カテゴリ 田村語り)江戸時代の東北地方では『田村の草子』を底本とした『田村三代記』が、奥浄瑠璃を語る目盲法師の代表的演目として各地で流布されたことで巷に広がりをみせ、地方伝説として伊達藩を中心に岩手県や宮城県、奥羽山脈を越えた秋田県にまで定着、上演された社寺の縁起などに取り込まれた。多くは坂上田村麻呂伝説として伝説上の人物である坂上田村…61キロバイト (10,532 語) - 2024年5月18日 (土) 07:09
- 大嶽丸 (カテゴリ 田村語り)一方では鎌倉時代初期(1195年頃)に成立したと推定される歴史物語『水鏡』によると、平城太上天皇が軍をおこして尚侍藤原薬子と同じ輿に乗り東国へ向かったことを大外記上毛野穎人が嵯峨天皇に申し、前日大納言に任命された坂上田村麻呂は宰相文室綿麻呂を遣わしてその道を遮り、藤原仲成を射殺したという。この頃より平城上皇の剃髪入道や薬子…35キロバイト (6,133 語) - 2024年1月10日 (水) 03:38
- 慶長7年(1602年)5月、改易を受けた義胤は三春領内大倉(田村市)一時移住することにしたが、この時三春城代であった蒲生郷成と「御入魂」の間柄になったという。(相馬藩世紀・戦国時代の相馬) 義胤が最晩年(80代)の頃に江戸城に登城した折、城内に入って下馬した時に丁度政宗が退出してきたが、政宗はすぐには輿…57キロバイト (10,365 語) - 2024年2月27日 (火) 22:07
- 明治6年 - 窪屋郡沖村に要知小学、四十瀬村に明新小学、福井村に惜陰小学と行輿小学、白楽市村に進徳小学が開校。 明治13年 - 要知小学と明新小学が合併し沖小学校を開校。また惜陰小学を富井小学校、行輿小学を笹沖小学校に、進徳小学を日吉小学校に改称。 明治20年 -…20キロバイト (3,295 語) - 2024年5月23日 (木) 01:45
- 和宮の居室に潜み、そのお下がりを食べ、声も出せない毎日を送ることになる。文久元年(1861年)4月21日、橋本邸に里帰りする和宮の輿にフキもともに乗り込んだが、帰りの輿に宮の姿はなく、それからフキは宮の替え玉として、「乳人(めのと)」少進にかしづかれながら、拝謁を受け、読めない字の手習いをし、茶道…11キロバイト (1,650 語) - 2024年2月17日 (土) 04:27
- 天平勝宝元年(749年)聖武天皇が国家のシンボルとして奈良の大仏を建設するとき、宇佐八幡神は天皇と同じ金銅の鳳凰をつけた輿に乗って入京し、これを助けた。 神護景雲3年(769年)、天皇の位を狙っていた道鏡は、称徳天皇によって道鏡を次の皇位継承者に指名させようとして、「道…26キロバイト (4,113 語) - 2024年6月9日 (日) 10:03
- 姓(やさくのかばね)のうち第七位とされていた。 讃岐国山田西分村の七郎岡城城主安達七郎常清之又、三日城、常清の柴城とある。 芸藩通志に「花原城は安達輿三左衛門居る所」とある。 丹波志に「安達氏の古城遠坂城あり、」同郡足立氏と同族か、當城主京之助は弓衛の達人也という。また玄蕃和泉守とある。…15キロバイト (1,848 語) - 2024年6月4日 (火) 14:29
- 内藤正典 中川浩一 長久保赤水高 中澤高志 中島峰広 中田高 中西僚太郎 中野尊正 長野覚 中目覚 中村和郎 中谷友樹 中山貞治 西亀正夫 西川治 西田輿四郎 西村嘉助 西村睦男 沼尻墨僊 能登志雄 野原敏雄 野間三郎 野間晴雄 野村正七 橋詰直道 橋本雄一 長谷川典夫 花井重次 林紀代美 林上 原口剛…9キロバイト (1,002 語) - 2024年4月18日 (木) 14:08
- 、太美山村、東太美村、吉江村、東礪波郡北山田村及び山田村が合併して、西礪波郡福光町が発足する。 石黒村の1915年末の人口は1530人である。 農業 『大日本篤農家名鑑』によれば石黒村の篤農家は、「池田太郎平、石崎吉蔵、石崎幸吉、河合十郎、河合八十八、河合輿三郎、堀田久一郎」などである。 医師 河合忠次…3キロバイト (337 語) - 2024年5月29日 (水) 01:10
- その後も大きな開発は進まなかったが、昭和50年(1975年)頃から宅地化が急速に進み、輿山丘陵に青山台が開発されることとなった。 1889年(明治22年) - 藤尾村・西畑村・鬼取村・小倉寺村・大門村・有里村・壱部村・小瀬村・乙田村・小平尾村と合併して南生駒村が発足。南生駒村大字萩原となる。 1955年(昭和30年)…10キロバイト (904 語) - 2023年12月1日 (金) 16:52
- 3DCG:秋里直樹、平山智則、武井裕介 CG送出:齋藤芳崇、宮下幸恵、当銀優季、竹内佐織、木村健史郎 美術協力:東宝舞台、チトセアート、エスケイシステム、ヤマモリ、ナカムラ総美、輿進電化、テルミック、野沢園、京阪商会、テレフィット、神田屋、京花園、千葉洋行、東京衣裳、山田かつら、東京特殊効果、ファイバーワーク フジテレビ・オール美術スタッフ…48キロバイト (6,116 語) - 2024年6月3日 (月) 21:08
- 板部岡江雪斎の子の岡野房次が徳川家宣に従い、甲府藩臣より移った。 岡部家 4,500石 上総国夷隅郡・長柄郡・埴生郡・武射郡・市原郡。下総国匝瑳郡、上野国邑楽郡・勢多郡内 初代・岡部輿賢は徳川秀忠に、2代・勝政は徳川家綱に近侍した。 岡部家 3,000石 三河国宝飯郡・額田郡・幡豆郡内 初代・岡部定直は甲府藩御附家老より移った。 岡部家…66キロバイト (11,473 語) - 2024年5月19日 (日) 19:19
- 人であった熊谷直好と共に桂園派の二高弟と称された[要出典]。1845年(弘化)2年、直好と歌論に関する論争を行った。 1863年(文久3年)郁姫の入輿に伴って近衛家に仕え、勤王運動に関わった。明治維新後、神祇省と文部省を兼務し、1871年(明治4年)宮内省に出仕した。翌年歌道御用掛を命じられ、宮廷…5キロバイト (439 語) - 2024年2月24日 (土) 16:51
- 13年)…呼韓邪単于の子、車牙若鞮単于の弟 烏累若鞮単于(咸、在位:13年 - 18年)…呼韓邪単于の子、烏珠留若鞮単于の弟 呼都而尸道皋若鞮単于(輿、在位:18年 - 46年)…呼韓邪単于の子、烏累若鞮単于の弟 烏達鞮侯単于(烏達鞮侯、在位:46年)…呼都而尸道皋若鞮単于の子 孝単于(咸、在位:11年…16キロバイト (2,907 語) - 2023年9月15日 (金) 05:10
- 生駒市南部にあり、西に小倉寺町、大門町、南に萩原町、青山台、東に小瀬町、東から北にかけて壱分町と接している。 生駒山から伸びる二つの尾根先・文殊山と輿山の間に位置する。 有里川 - 竜田川の支流。 有里は奈良盆地に条里制が敷かれた頃、里と呼ぶ集落名を付けたことに始まるとされる。…10キロバイト (848 語) - 2023年11月23日 (木) 22:18
- 献上された仏像を、蘇我稲目が小墾田の家に安置し、その後向原の家を浄(きよ)め捨(から)ひて寺とした。その後、国内に疫病が流行したため、排仏派の物部尾輿と中臣鎌子はこれを外国の神である仏像を祀ったことに対する日本の神の怒りであるとして、仏像を難波 (なにわ) の堀江に捨て、伽藍を焼き払ってしまった。…6キロバイト (950 語) - 2023年10月26日 (木) 12:26
- 邑あり、又三代實録、貞觀二年、三月廿一日、薩摩國鹿兒島神、この鹿兒島神、蓋し本府草年田村宇治瀬神なりと云、又建久八年、六月、薩摩國圖田帳に、大隅正八幡宮御領八十町、鹿兒島郡荒田荘とあり、かゝれば往古國分より本府荒田村の邊、彦火火出見尊に縁由ある故蹤にて、鹿兒島と稱へ、今の鹿兒島郡より以北、國分の地に