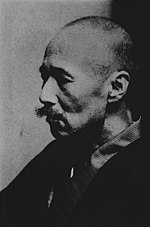検索結果
このウィキでページ「篁村街」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 日本では1887年(明治20年)に、饗庭篁村によって「ルーモルグの人殺し」として初めて翻訳(翻案)された(『読売新聞』12月14日、23日、27日)。篁村は同年11月に「黒猫」の翻訳も発表しており、これが日本におけるポー作品の初の翻訳紹介となった。ただし、これは外国語が苦手であった篁村…23キロバイト (3,585 語) - 2023年10月22日 (日) 10:48
- 1927年(昭和2年)1月から、『黒潮』(くろしお)と改題し、同年3月まで3号のみ発行した。 1889年(明治22年)1月、須藤南翠、森田思軒、饗庭篁村、石橋忍月、依田学海、山田美妙らからなる14名の文学同好会が編集し、発行した。翌年1890年(明治23年)6月、1年半で第1次『新小説』の刊行は終了する。…6キロバイト (581 語) - 2023年4月8日 (土) 13:58
- 日本のテレビアニメ『吸血姫美夕』第九話「あなたの家」も本作のオマージュである。 日本では1887年(明治20年)、饗庭篁村によって初めて翻訳された。これは日本におけるポー作品の最初の翻訳でもある。ただしこれは外国語の得意でない饗庭が友人に口訳してもらい、それをもとに意訳…12キロバイト (1,683 語) - 2023年12月24日 (日) 18:52
- 日本においては1887年(明治20年)、饗庭篁村の和漢混淆体よる翻訳「黒猫」(『読売新聞』11月3日・9日に掲載)、「ルーモルグの人殺し」(同12月14日・23日・27日)、「眼鏡」(翌1月3日-20日)によって初めて翻訳紹介された。これらは外国語が苦手であった篁村…88キロバイト (13,278 語) - 2024年5月7日 (火) 11:41
- 上林暁・酒場小説集』(ちくま文庫 1999.9) 『明治文学遊学案内』(筑摩書房 2000.8) 『文藝春秋 八十年傑作選』(文藝春秋 2003.3) 『饗庭篁村 明治の文学 第13巻』(筑摩書房 2003.4)- 同シリーズ:全25巻の編集も務めた。 『日本近代文学評論選 明治・大正篇』(千葉俊二共編 岩波文庫…29キロバイト (3,849 語) - 2024年5月31日 (金) 21:51
- 矢野文雄(開校時の講師、創立委員(慶応卒)) 尾崎行雄(慶応中退) 市島謙吉(ジャーナリスト、衆議院議員(東大中退)) 坪内逍遥(上古史、中古史、文学士(東大卒)) 饗庭篁村(日本人で初めてエドガー・アラン・ポーの作品を翻訳) 秋山雅之介(国際法学者、朝鮮総督府司法部長官、法政大学学長) 朝倉外茂鉄(羅馬法、海啇、擬律擬犯…58キロバイト (7,461 語) - 2024年5月11日 (土) 22:14
- 水戸徳川邸舊阯」の石碑があり、聖徳記念絵画館には木村武山筆『徳川邸行幸』が収められている。 徳川昭武 1853~1910 水戸徳川家11代当主 饗庭篁村 1855〜1922 小説家、劇評家 徳川篤敬 1855〜1898 水戸徳川家12代当主、侯爵 森鷗外 1862〜1922 小説家、軍医…59キロバイト (8,118 語) - 2024年4月13日 (土) 03:10
- 収録作品: 〔明治・大正〕:福澤諭吉「かたわ娘」、山田美妙「胡蝶」、坪内逍遥「細君」、尾崎紅葉「拈華微笑」、森鷗外「舞姫」、幸田露伴「對髑髏」、饗庭篁村「腹の子」、樋口一葉「たけくらべ」、斎藤緑雨「おぼろ夜」、国木田独歩「春の鳥」、川上眉山「ふゆだすき」、正宗白鳥「塵埃」、三島霜川「解剖室」、眞山青…52キロバイト (7,297 語) - 2024年2月1日 (木) 23:17
- は小倉に転勤するまでつづき、不折とは生涯続いた。 ^ 1月に創刊された『めさまし草』は、3月から「三人冗語」が掲載され、9月以降これに依田学海、饗庭篁村(あえば こうそん)、森田思軒、尾崎紅葉らが加わり、「雲中語」として評判になった。紅葉、川上眉山、正岡子規、高浜虚子、落合直文などが文を寄せた。また…165キロバイト (23,715 語) - 2024年5月1日 (水) 16:45