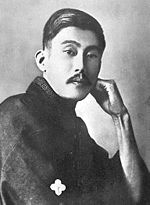検索結果
表示
このウィキでページ「書堂巖」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 巖谷 小波(いわや さざなみ、1870年7月4日(明治3年6月6日) - 1933年(昭和8年)9月5日)は、明治から大正にかけての作家、児童文学者、口演童話家、俳人、ドイツ文学者、ジャーナリスト。本名は季雄(すえお)。別号に漣山人、楽天居、大江小波等がある。…18キロバイト (2,381 語) - 2023年12月7日 (木) 12:59
- 巖谷 一六(いわや いちろく、天保5年2月8日(1834年3月17日) - 明治38年(1905年)7月12日)は、近江国(滋賀県)出身の書家、官僚、漢詩人。本名は修(しゅう)(幼名は辨治、ついで迂也)、字は誠卿。特に書家として名高く、一六(一六居士)はその号で、別号に迂堂…10キロバイト (1,644 語) - 2024年5月9日 (木) 13:09
- 宮本武蔵 (カテゴリ 日本の能書家)巖流島の闘いで用いた櫂の木刀を自分で復元し剣術に用いていた。 吉岡家の断絶は、武蔵が当時における、武者修行の礼儀を無視した形で勝負を挑んだため、さながら小規模な合戦にまで勝負の規模が拡大し、吉岡がそれに敗れてしまったためである。 武蔵没後21年後の寛文6年(1666年)に書…71キロバイト (10,795 語) - 2024年6月8日 (土) 15:41
- 綺堂:岡本綺堂で知られる。岡本敬二。 魯庵:内田魯庵で知られる。内田貢。 介山:中里介山で知られる。中里弥之助。 烏石:松下烏石で知られる。松下辰。 小波:巖谷小波で知られる。巖谷季雄。 思軒:森田思軒で知られる。森田文蔵。 如是閑:長谷川如是閑で知られる。長谷川萬次郎。 雪嶺:三宅雪嶺で知られる。三宅雄二郎。 乙羽:大橋乙羽で知られる。大橋又太郎。…7キロバイト (895 語) - 2023年4月1日 (土) 06:34
- 巻菱湖(1777年 - 1843年) 中沢雪城(1810年 - 1866年) 金井金洞(1833年 - 1907年) 巖谷一六(1834年 - 1905年) 辻香塢(1863年 - 1947年) 西川春洞(1847年 - 1915年) 諸井春畦(1866年 - 1919年)…10キロバイト (1,539 語) - 2023年3月24日 (金) 21:04
- 土門拳賞 石川直樹『CORONA』(第30回・2010年) サントリー学芸賞 小泉文夫『民族音楽研究ノート』(第2回芸術・文学部門・1980年) 松山巖『うわさの遠近法』(第5回社会・風俗部門・1993年) 野崎歓『ジャン・ルノワール 越境する映画』(第23回社会・風俗部門・2001年) 小谷野敦『聖母のいない国――The…11キロバイト (1,330 語) - 2023年7月22日 (土) 23:45
- 日本の書道史 (カテゴリ 日本の書)書は唐様と和様に二分されたのである。 六朝書道の盛行と上代様の復興 明治時代に入り、この時代の実権者の多くが漢学の素養があったことから唐様の書風に傾いていった。そして清国の楊守敬が漢魏六朝の碑帖を携えて来日し、日本の書道界に大きな衝撃を与え、この影響により巖…106キロバイト (11,934 語) - 2024年5月28日 (火) 23:49
- 佐藤誠三郎(1982-98、政治経済) 細谷千博(1982-90、政治経済) 日下公人(1982-98、社会風俗) 山本七平(1982-91、思想歴史) 中谷巖(1985-2000、政治経済) 村上泰亮(1985-92、政治経済) 芳賀徹(1985-2010、社会風俗→藝術文学) 西部邁(1985-92、思想歴史)…72キロバイト (946 語) - 2024年4月6日 (土) 02:04
- おおい町(日本) 紅毛城 淡水イギリス領事官邸 滬尾砲台 前清淡水税関吏官邸(小白宮) 重建古街 牛津学堂(真理大学) 私立淡江高級中学 淡水礼拝堂 淡水紅楼 清水巖祖師廟 鄞山寺 福佑宮 淡水竜山寺 淡水老街 天元宮 漁人桟橋 情人橋 淡水港 沙崙海水浴場 油車口忠義宮 一滴水記念館 淡水街長多田栄吉故居…8キロバイト (608 語) - 2024年4月24日 (水) 06:36
- が10月30日、自宅で没した。享年35。戒名は彩文院紅葉日崇居士。紅葉の墓は青山墓地にあり、その揮毫は、硯友社の同人でもある親友巖谷小波の父で明治の三筆の一人といわれた巖谷一六によるものである。 紅葉の作品は、その華麗な文章によって世に迎えられ、欧化主義に批判的な潮流から、井原西鶴を思わせる風俗描…22キロバイト (3,598 語) - 2024年2月17日 (土) 05:43
- 2002年) 『差異の事件誌――植民地時代の異文化認識の相剋』(巖南堂書店, 1984年) 『東南アジア世界の構造と変容』(創文社, 1986年) 『講座東南アジア学(4)東南アジアの歴史』(弘文堂, 1991年) 『講座仏教の受容と変容(2)東南アジア編』(佼成出版社, 1991年)…12キロバイト (1,331 語) - 2024年1月30日 (火) 12:14
- 路上観察と心理学的街遊びのヒント 小林茂雄, 東京都市大学小林研究室 著 誠信書房 2010年 えひめユーモア図鑑 : ユーモア路上観察展10周年記念 乗松巖記念館「エスパス21」 企画・編集 乗松巖記念館「エスパス21」 2012 パパのいうことを聞きなさい! : 路上観察研究日誌 1-4 松智洋 原作,宮乃ひろつぐ 漫画 集英社…8キロバイト (1,149 語) - 2024年2月16日 (金) 08:18
- 志半ばにして、翌年、74歳で没する。 門人は3,000人に及んだといわれる。門弟として富士谷成章(実弟)・巖垣龍渓・稲毛屋山・小浜清渚・東条一堂・北条霞亭などがいる。 京極の阿弥陀寺に葬られた。墓誌は松浦清が文を製し、その書は本多康完が記した。東京国立博物館には「明経先生像」と題された淇園の遺像が残る(渡辺南岳筆、東京国立博物館…5キロバイト (641 語) - 2023年7月12日 (水) 07:05
- 書辞典』を発表、作家デビュー、21世紀までミステリー作品を発表している。 1992年に、ジャストシステムのかな漢字変換ソフトウェア「ATOK」の「ATOK監修委員会」の座長を務める。 1993年に、『少年小説大系』(全32巻、小田切進・尾崎秀樹共同監修、三一書房)により、第16回巖谷小波文芸賞受賞。…23キロバイト (3,385 語) - 2024年4月22日 (月) 04:59
- 中林梧竹 (カテゴリ 日本の能書家)1913年(大正2年)87歳の生涯を閉じた。 明治書家にあっては珍しい造形型を追求した独特の書風を確立し、その新書風で書壇への影響力が大きかった。六朝の書法を探究して、多くの碑拓を請来したため、書というよりもむしろ絵画の味わいがある。また、水墨画も数多く残している。 同じく「明治の三筆」に数えられる日下部鳴鶴や巖…4キロバイト (596 語) - 2023年9月15日 (金) 08:03
- 1981 - 1982。編集委員 『忠臣蔵銘々伝 物語と史蹟をたずねて』監修、成美堂出版、1982 のち成美文庫 『歴史小説・時代小説総解説』監修、自由国民社 1984 『ふくしまの文学』全3巻 福島民報・寿ビル編、巖谷大四, 伊藤桂一, 河野保雄, 佐藤善信と責任編集 福島民報社 1985 『歴史の群像…32キロバイト (5,220 語) - 2024年6月1日 (土) 07:40
- 海外においては貧困国にも第二代宗家保巖が訪れて空手の指導を行うとともに、学校建設等の社会貢献活動を行っていた。 初代宗家保勇十段範士が現役の時代は全日本空手道連盟(旧)から脱退後は他流派との交わりを禁止しており、現在も一流一派を継承している。2000年(平成12年)5月31日に初代宗家保勇が死去して第二代宗家を保巖…16キロバイト (2,224 語) - 2024年4月27日 (土) 22:45
- 中沢雪城 (カテゴリ 日本の能書家)慶応2年2月1日(1866年3月17日))は、江戸時代後期に活躍した書家。名は俊卿、字は子国、通称を行蔵という。雪城は号で雪生とも号した。堂号は蕭間堂。 巻菱湖(幕末の三筆の一人)の高弟で、流麗な書風をもって大いに流行し、菱湖四天王の一人に数えられた。雪城の門下から巖谷一六・西川春洞・金井金洞の大家が輩出した。…3キロバイト (496 語) - 2020年8月13日 (木) 10:32
- 押)し流されてゐるべきときではない。急流を遡るといふ巖の樣に、それに逆らつて、立たねばならぬ。おう、力よ、湧け。 隅に變つてゆく竹がキキキと音をたてた。純一は立上つて東に向いた明り窓の外の炭俵から炭を出した。星は空に强く冷〔た〕い光を放つて、眞如堂にあたる杉木立の梢は黑々と見えた。ほっと吐いた息が直ぐに凍つて冷〔た〕い夜氣に溶けた。