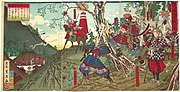検索結果
このウィキでページ「府城砦」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 生し、三河国の徳川家康と相模国の北条氏直が甲斐へ侵攻した。天正壬午の乱において徳川勢は新府城を本陣に、能見城など七里岩台上の城砦に布陣した。対して後北条氏は都留郡を制圧し、若神子城に本陣を置くと同様に周辺の城砦に布陣し、徳川勢と対峙した。同年10月には徳川・北条同盟が成立し、後北条氏は甲斐から撤兵する。…15キロバイト (2,309 語) - 2024年1月13日 (土) 06:25
- 八ヶ岳南麓・七里岩台上に布陣して対峙し、北条氏直が北杜市須玉町若神子の若神子城に布陣して北杜市域の城砦に布陣したのに対し、徳川家康は甲府から新府城に本陣を移転し、能見城・白山城をはじめとする市域の城砦にも布陣した。 同年10月29日には徳川・北条同盟が成立すると後北条氏は撤兵し、甲斐は家康が領する…30キロバイト (3,490 語) - 2024年3月10日 (日) 12:47
- 信龍の屋敷は、近世の絵図類によれば現在の甲府市北新一丁目に所在し、一条小路と呼ばれる甲府城下の南北基幹街路の一角に位置する。天正10年6月の本能寺の変後に武田遺領をめぐり発生した天正壬午の乱では、甲斐において相模国の北条氏直と徳川家康が対峙し、北杜市須玉町若神子に本陣を置き、北杜市域の城砦群に布陣した北条勢に対し、徳川勢は七里岩南端の韮…7キロバイト (844 語) - 2023年10月5日 (木) 04:36
- 柴峠砦 三日城 新宮城 富来城 木尾嶽城 一乗谷城 福井城(北ノ庄城) 金ヶ崎城 敦賀城 疋壇城(塩山城) 玄蕃尾城(内中尾山城) 丸岡城 杣山城 小丸城 大野城 勝山城 三国湊城 後瀬山城 小浜城 国吉城 高浜城 箱ヶ岳城 躑躅ヶ崎館(武田氏館) 甲府城(舞鶴城・一条小山城・府中城) 新府城 白山城…77キロバイト (5,885 語) - 2024年5月29日 (水) 03:36
- 武田勝頼 (新府城の築城と甲江和与の模索の節)機に領国の動揺を招き、その後の長尾上杉氏との甲越同盟、佐竹氏との甲佐同盟で領国の再建を図り、織田氏との甲江和与も模索し、甲斐本国では躑躅ヶ崎館より新府城への本拠地移転により領国維持を図るが、織田信長の侵攻である甲州征伐を受け、天正10年(1582年)3月11日、嫡男・信勝とともに天目山で自害した。こ…59キロバイト (10,061 語) - 2024年5月13日 (月) 14:50
- 韮崎市中田町中條には武田勝頼の築城した新府城が所在している。天正10年(1582年)2月28日には、勝頼は織田信長・徳川家康連合軍の武田領侵攻に際して諏訪上原城を退去し新府城に入り、3月3日には新府城を放棄し、甲府城下の一条信龍屋敷(甲府市北新)で休息し、郡内へ向けて勝沼・田野…5キロバイト (803 語) - 2023年11月14日 (火) 14:05
- 6月の天正壬午の乱では、信濃国から相模国の北条氏直が甲斐へ侵攻し、若神子城に本陣を起き周辺の城砦に布陣した。これに対し、三河国の徳川家康は現在の韮崎市中田町中條に所在する新府城に本陣を起き、七里岩台上の城砦に布陣し、北条勢と対峙した。同年10月には徳川・北条同盟が成立し、氏直は甲斐・都留郡から撤兵した。…4キロバイト (587 語) - 2023年2月22日 (水) 00:43
- は相模国の北条氏直と徳川家康が対峙し、家康ははじめ甲府市の尊躰寺(甲府市城東)・一条信龍屋敷(甲府市北新)、後に韮崎市の新府城に本陣を置いた。対して北条勢は現在の北杜市一帯の城砦に布陣した。徳川軍の布陣のなかでは甲府市御岳町に御嶽衆や下伊那衆の知久頼氏が配置され甲府の背後を監視し、同様に下芦沢の御嶽…13キロバイト (1,968 語) - 2024年5月25日 (土) 16:35
- 府城を放棄し、廃城にした。そして郡内の小山田信茂を頼って別の城(岩殿城)に向かった。この時、新府城はまだ築城途中の城であり、櫓も未完成で防御力は乏しく、籠城で戦うには不向きな城であった。城内には多くの武士、兵士や妻子、人質が取り残されたままであったが、それでも新府城には火が放たれた。…46キロバイト (7,774 語) - 2024年1月22日 (月) 01:57
- 斐善光寺、時宗寺院の一蓮寺、臨済宗寺院の円光院、長禅寺、東光寺、法泉寺、曹洞宗寺院の、大泉寺や恵雲院、日蓮宗寺院の信立寺がある。 主な城郭・砦 勝山城 甲府城跡(舞鶴城公園、県指定史跡) 躑躅ヶ崎館(国の史跡) 要害山城(国の史跡) 主な寺院 一蓮寺 円光院(甲府五山) 塩沢寺 円楽寺 遠光寺 甲斐善光寺…79キロバイト (8,863 語) - 2024年5月27日 (月) 10:41
- 府城に本拠を置くと、北杜市須玉町若神子の若神子城に本陣を置いた後北条勢に対して七里岩台上の城砦に軍勢を配置し、御岳においても甲府市御岳町の御岳城、甲斐市下芦沢の御岳芦沢小屋(平見城の烽火台)に御岳衆らの兵が配置された。 江戸時代に荒川上流の猪狩村(甲府市猪狩町)と周辺諸村は製炭が盛んで、甲府城…23キロバイト (3,619 語) - 2024年4月5日 (金) 05:32
- たものは一級、二級、三級と区分され、それ以降は保護機関の名称(国定は行政院文化建設委員会を経て文化部)が使用されている。 台湾の都市の発展は台南台湾府城と台北艋舺を中心とし、領地には百ヶ所を越える史跡が指定されている。それ以外には清朝統治時代に淡水庁が設置されていた新竹(竹塹)や、台湾海峡の中継地点…80キロバイト (319 語) - 2024年6月4日 (火) 13:04
- 田中城は天文6年(1537年)に駿河今川氏によって築かれた。永禄13年(1570年)の武田氏による駿河侵攻以降、三河の徳川氏に対抗する駿河西部の城砦網の要として重要視された。 永禄13年(1570年)正月、武田信玄により攻め落とされ、馬場信春により改修。田中城に改名。武田家家臣山県昌景が入城。…9キロバイト (1,164 語) - 2024年2月26日 (月) 05:30
- 生する。天正壬午の乱において甲斐は三河国の徳川家康と相模国の北条氏直が争奪し、家康が新府城(韮崎市中田町中條)を本陣に七里岩台上の城砦に布陣したのに対し、後北条氏は若神子城(北杜市須玉町若神子)を本陣に、周辺の城砦に布陣した。この時、後北条氏は谷戸城へも布陣していたという。…8キロバイト (1,166 語) - 2023年12月2日 (土) 16:06
- を通じて戦争がなかったことと、大半の藩主家が領主の交代を経験しており、(石高は別として)土地自体への執着が薄かったことが理由として挙げられる。また、城砦としての防衛能力を重視した場所は必ずしも交通の便が良いところではなく、交易都市の色彩を強めるにつれ城が放棄され陣屋などに行政中心が移ったケースも多い。…25キロバイト (3,176 語) - 2024年2月2日 (金) 09:41
- 一政父子が不在の隙に亀山城、峯城、関城、国府城、鹿伏兎城を調略、亀山城に滝川益氏、峯城に滝川益重、関城に滝川忠征を置き、自身は長島城で秀吉を迎え撃った。秀吉は諸勢力の調略や牽制もあり、一時京都に兵を退いていたが、翌月には大軍を率いこれらへの攻撃を再開、国府城を2月20日(4月11日)に落とし、2月中…23キロバイト (3,512 語) - 2024年6月7日 (金) 21:14
- 韮崎には武田氏が拠り、北杜市大泉町の谷戸城などこの時期の中世城郭や砦が分布する。戦国時代には戦国大名となった武田氏が信濃侵攻を行う中継地点にもなり、武田勝頼の時代には現在の韮崎市中田町には新府城が築城され府中の移転が試みられ、新府城は台地の残丘を利用している。…6キロバイト (936 語) - 2022年11月18日 (金) 05:30
- 天正10年(1582年)6月は本能寺の変により甲斐・信濃の武田遺領を巡る「天正壬午の乱」が発生し、三河国の徳川家康は韮崎市中田町中條の新府城を本陣に七里岩台上の城砦に分布し、若神子城に本陣を置く後北条氏と対峙した。松雲寺塁は小田川沿いの逸見路に立地し、一帯の水上氏屋敷も徳川方が布陣したと見られている。…4キロバイト (529 語) - 2023年12月14日 (木) 10:24
- せしむ、その頃福島左衛門太夫正則・池田三左衛門輝政に向ひいひけるは、近年江戸・駿河両城の経営ありて、諸大名みなこれが為に疲弊せり、されどいづれも天下府城の事なれば、誰も労せりとも覚えざるなり、この名古屋は末々の公達の居城なるを、これまで我等に営築せしめらるゝはあまりの事なり、御辺は幸大御所の御ちなみ