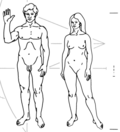検索結果
このウィキでページ「存古閣」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 十三史に『南史』・『北史』・『唐書』・『五代史』を加えたもの。宋代の標準であり、『三字経』にも「十七史、全在茲」という。宋以降にも十七史の名は使われ、毛晋は汲古閣本十七史を出版した。王鳴盛の『十七史商榷』が有名だが、この著書は『旧唐書』と『旧五代史』を含んでいるために実際には十九史になっている。なお宋の目録類…15キロバイト (1,514 語) - 2024年1月21日 (日) 05:30
- 業出版が発達し、出版点数が飛躍的に増えたのは明時代中期以降である。明時代からは、多色印刷(套印)も行われた。古書を収集し、良版の刊行を行う毛晋 (汲古閣) のような蔵書家も現れた。小説の出版も盛んで、いわゆる四大奇書の完成と出版も明時代末期である。 清時代には、膨大な編纂事業が宮廷によって行われた。…14キロバイト (2,416 語) - 2023年9月18日 (月) 03:07
- 『四庫全書総目提要』巻123・子部33・雑家類7・説郛120巻 『四庫全書総目提要』巻132・子部42・雑家類存目9・続説郛46巻 昌彼得『説郛考』文史哲出版社、1979年(原著1962年)。 徐三見「汲古閣蔵明抄六十巻本《説郛》考述」『東南文化』第106号、112-127頁、1994年。http://vip…5キロバイト (902 語) - 2021年5月15日 (土) 06:48
- NCID BN09655944。全国書誌番号:57004529。 橋本節哉編 編『白沙村人随筆』中央公論社、1977年8月。全国書誌番号:77025727。 『存古楼清秘録』橋本関雪、1919年10月。 NCID BA82706649。全国書誌番号:43034237。 『不離心帖』橋本関雪、1933年4月。…24キロバイト (2,770 語) - 2024年5月13日 (月) 09:12
- 古活字本では「井官」のように書かれている。汲古閣本、『太平御覧』鱗介部八・鯉魚に引く『孔子家語』、百衲本『史記』孔子世家の『索隠』に引く『孔子家語』は、いずれも「上官」に作る。 碑文資料では、後漢の永寿2年(156年)に隷書で刻まれた『礼器碑』に2回「并官」が見える。 「亓官」は沢存…6キロバイト (947 語) - 2023年11月21日 (火) 14:55
- 丁仁・高時敷・葛昌楹・兪人萃共編『丁丑劫餘印存』 郭宗昌『松談閣印史』 『君台観左右帳記事』(唐ゐんつくし)理右衛門刊 1643年 『和漢歴代画師名印冩図』1647年 藤原惺窩『皇朝集古印譜』(伝存せず) 榊原篁洲『芸窗酔銕』1699年(伝存せず) 細井広沢・細井九皋『奇勝堂印譜』 池永道雲『一刀万象』1713年…4キロバイト (725 語) - 2021年3月14日 (日) 17:26
- 六朝之鬼神誌怪書(上)に「其書今具存,亦記靈異變化之事如前記,陶潛曠達,未必拳拳於鬼神,蓋偽托也。」 ^ 『国訳漢文大成 第十二卷』, p. 14 影印 17コマ. ^ 毛晋の書斎名をとって汲古閣本といわれる。明の万暦31年に刊行された『秘冊彙函(ひさついかん)』…4キロバイト (678 語) - 2023年7月7日 (金) 02:23
- 黄虞稷(中国語版)『千頃堂書目(中国語版)』は後に『明史』芸文志の基礎となった。他に祁承㸁(中国語版)『澹生堂書目』、銭謙益『絳雲楼書目』、毛晋『汲古閣蔵書目』なども著名である。銭曾(中国語版)の『読書敏求記(中国語版)』は珍しい本を入手した際にそれを記録した目録で、最初の珍本収蔵の解題である。…64キロバイト (10,078 語) - 2024年1月11日 (木) 07:12
- 梁臣伝第九 - 敬翔・朱珍・龐師古・葛従周・霍存・張存敬・符道昭・劉捍・寇彦卿 梁臣伝第十 - 康懐英・劉鄩・牛存節・張帰覇・王重師・徐懐玉 梁臣伝第十一 - 楊師厚・王景仁・賀瓌・王檀・馬嗣勲・王虔裕・謝彦章 唐臣伝第十二 - 郭崇韜・安重誨 唐臣伝第十三 - 周徳威・符存審・史建瑭・王建及・元行欽・安金全・袁建豊・西方鄴…9キロバイト (1,503 語) - 2022年6月22日 (水) 00:03
- 1794年)、「孟楼」と改称。光緒元年(1875年)は楼を重修した。古い名前を回復する。 澄鮮閣:澄鮮閣は、北宋の崇寧元年(1102年)の創建で、初名は水陸閣。万暦十年(1591年)は楼を重修した、「澄鮮閣」と改称。南朝宋初の郡守である謝霊運はこの島に、「乱流趨正絶、孤嶼媚中川。雲日相輝映、空水共澄…7キロバイト (844 語) - 2023年3月19日 (日) 04:39
- の時代が焚書坑儒以前であったため、日本には「逸書百篇」(失われた『書経』の篇)が残る、といっている。もちろんこれは詩的誇張にすぎないが、日本に残る佚存書に言及したものとして注目される。 『日本刀歌』は中国人の日本観のみならず、日本人の歴史観にも影響を及ぼした。『神皇正統記』の中で、「始皇帝が日本に…10キロバイト (1,560 語) - 2024年4月9日 (火) 03:54
- 関口 存男(せきぐち つぎお、正字は關口存男、1894年11月21日 - 1958年7月25日)は、日本のドイツ語学者(ゲルマニスト)。通称:ゾンダン(ドイツ語のsondernにかけてある)。 ドイツ語以外にも様々な言語に通じており、「不世出の語学の天才」と呼ばれた。また、村田実らの新劇運動に参加、…47キロバイト (7,396 語) - 2024年2月22日 (木) 14:18
- 山崎覚士「五代政治史研究の成果と課題」(『中国五代国家論』(思文閣出版、2010年)序章) ^ a b c 山崎覚士「五代の〈中国〉と平王」(初出:宋代史研究会研究報告第九集『「宋代中国」の相対化』(汲古書院、2009年/所収:山崎『中国五代国家論』(思文閣出版、2010年)) ^…30キロバイト (4,793 語) - 2024年5月31日 (金) 23:18
- 堂関白記」の呼称は江戸時代にはすでに通称になっていたようである。 平安末期までに36巻が存したとされるが、現存するものは、長徳4年(998年)から治安元年(1021年)の間の記事で、直筆本14巻が伝わっている。古写本の筆者について従来道長の長男頼通によるものとされていたが根拠は乏しく、現在は頼通の子…6キロバイト (944 語) - 2023年12月25日 (月) 09:03
- 堂文庫の16冊本、水戸彰考館の12冊本、岩瀬文庫の19冊本、東京国立博物館の37冊本を始め、諸本が多く伝存しているが、その間に内容の出入りが少なくない。刊本は、史料編纂所の編集にかかる『大日本古記録』に翻刻が収録され(全4冊完結)、岩波書店から出版されている。 今枝愛真 「後愚昧記」(『国史大辞典…4キロバイト (572 語) - 2023年9月7日 (木) 21:09
- 「安期先生図」や「晋明帝歩輦図」を画いたとされるが、彼の作品はひとつも伝存していない。また別体を創造したとされる。 古画品録 王伯敏 『中国絵画史事典』遠藤光一訳 雄山閣出版、1996年、ISBN 9784639013853 嶋田英誠 WEB版 中国絵画史辞典 (SHIMADA's…2キロバイト (283 語) - 2022年11月13日 (日) 10:24
- 尚書尭典(偽古文にては舜典)に詩言志、歌永言、声依永、律和声の句あり。此の中二句の永字を史記漢書王充論衡等に詠若くは咏に作れることあり。史記にては普通に行はるゝ諸本の中、及古閣本には歌長言、声依詠に作れり。〈五帝本紀〉漢書にては礼楽志に詩言志、歌咏言、声依咏に作り、芸文志には書曰、詩言志、哥詠言、故哀楽之心感、而哥詠之声発
- 傢(は簡体字では家に包摂される。)、𠖔(古字) 筆順 : 形声。「宀」+音符「𢑓 /*KA/」。「いえ」を意味する漢語{家 /*kraa/}を表す字。 「宀」+「豕」と分析する説があるが、これは誤った分析である。甲骨文字の形を見ればわかるように、「豕」(豚)とは関係がない。 唐蘭 『天壌閣甲骨文存考釈』 輔仁大学、1939年、35頁。
- 家物語などの中世の軍記物に多く用いられた用法。 ・草の陰 - 墓の下。墓。あの世。 ・条(でう) - ・・・ということ。・・・の件・ 語注 ・疎略を存ぜず - おろそかには存じておらず。 ・ - 。 ・ - 。 ・ - 。 大意 本文/現代語訳 語句(重要) ・ゆめゆめ -