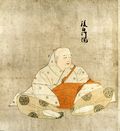検索結果
このウィキでページ「垂仲殿」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 皇を始祖とする「イリ王朝」「三輪王朝」説なども提唱されている。崇神・垂仁の二帝の名は和風諡号ではなく実名(諱)をそのまま記紀に記載した、とする説も存在する。 『日本書紀』は天智天皇7年(668年)の高句麗滅亡の記事で、この滅亡は仲牟王(東明聖王)が高句麗を建国してからちょうど700年目であったと記…32キロバイト (5,838 語) - 2024年6月8日 (土) 12:33
- 5月1日神服織機殿神社、神麻続機殿神社、各9時 10月1日神服織機殿神社、神麻続機殿神社、各8時 神御衣祭の付属祭祀。和妙(にぎたえ)・荒妙(あらたえ)の織り始めを神に奉告する。 神御衣奉織鎮謝祭(かんみそほうしょくちんしゃさい) 5月13日神服織機殿神社、神麻続機殿神社、各8時 10月13日神服織機殿神社、神麻続機殿神社、各8時…167キロバイト (23,788 語) - 2024年6月9日 (日) 11:14
- 誉津別命……垂仁天皇皇子。 五十瓊敷入彦命……垂仁天皇皇子。 稚城瓊入彦命……垂仁天皇皇子。 鐸石別命……垂仁天皇皇子。 池速別命……垂仁天皇皇子。 袁那弁王……垂仁天皇皇子。 祖別命……垂仁天皇皇子。 五十日足彦命……垂仁天皇皇子。 胆武別命……垂仁天皇皇子。 磐衝別王……垂仁天皇皇子。 伊登志別王……垂仁天皇皇子。…42キロバイト (6,297 語) - 2024年4月20日 (土) 02:18
- 大神を大和国の笠縫邑に祭らせたとあり、これが斎王(斎宮)の始まりとされる。そして次の垂仁天皇の時代、豊鍬入姫の姪にあたる皇女倭姫命が各地を巡行し伊勢国に辿りつき、そこに天照大神を祭った。この時のことを『日本書紀』垂仁天皇紀は「斎宮(いはいのみや)を五十鈴の川上に興(た)つ。是を磯宮(いそのみや)と…36キロバイト (4,172 語) - 2024年5月3日 (金) 10:27
- 菅原道真公(すがはらみちざねこう) 天穂日命(あめのほひのみこと) 覚寿尼公(かくじゅにこう)- 菅原道真公のおばに当たる人物。 埴輪を作って殉死の風習を変えた功績で、垂仁天皇32年に野見宿禰は土師臣(はじのおみ)の姓とこの地を与えられた。そして、その子孫である土師氏は野見宿禰の遠祖である天穂日命を祀る土師神社を建立…17キロバイト (2,336 語) - 2024年3月8日 (金) 12:52
- (12月23日) 大祓式 (12月31日) 建造物 本殿 - 昭和31年指定 申殿及び廊下 - 昭和42年指定 楼門 - 昭和42年指定 廻廊 - 昭和42年指定 (以下、附(つけたり)) 透塀 1棟 - 昭和31年指定(本殿と同時) 末社高良玉垂社本殿 - 昭和42年指定 末社常盤社新田霊社本殿 - 昭和42年指定…14キロバイト (1,862 語) - 2022年12月5日 (月) 14:30
- 追号の亀山院は、在所の名亀山殿にちなむ。父後嵯峨院が嵯峨野に建造した離宮亀山殿を伝領し、退位後は仙洞としてそこで崩御している。 ほかに、同じく父後嵯峨院が洛東東山禅林寺(永観堂)の南部に文永元年(1264年)に造営した離宮禅林寺殿に由来する禅林寺殿…17キロバイト (2,270 語) - 2023年5月21日 (日) 17:35
- ある洞院家は室町期に断絶したが、清華クラスの家柄であった。家名の由来は、正親町東洞院南西角に屋敷にあったことに由来しているが、その屋敷が土御門東洞院殿の裏築地に面していたことから、裏築地(うらついじ)もしくはそれが変じた裏辻(うらつじ)とも称した。後に分家した一流が「裏辻」と称したのはこれに由来し…12キロバイト (1,230 語) - 2023年5月21日 (日) 13:02
- 大嘗宮の儀(だいじょうきゅうのぎ) 125代天皇上皇明仁の大嘗祭の様子(平成2年(1990年)) 大嘗祭のこと。悠紀殿供饌の儀。主基殿供饌の儀。 大饗の儀 即位礼及び大嘗祭後神宮に親謁の儀 「明治天皇・神宮親謁」(松岡映丘画、池田仲博奉納) 即位礼及び大嘗祭後神武天皇山陵及び前四代の天皇山陵に親謁の儀 即位礼及び大嘗祭後賢所に親謁の儀…24キロバイト (4,067 語) - 2024年5月30日 (木) 01:55
- 一門で荼毘に付されていたのは崇源院だけであった。 民部卿局 京殿:浅井亮政の娘。浅井又次郎の妻。はじめは兄、浅井久政の侍女。法名は永信。 按察使局 海津局 近江局:浅井亮政の娘。斎藤義龍の妻。浅井家と六角家の仲が険悪化し、六角氏と懇意の仲にあった斎藤家から離縁された。…32キロバイト (4,711 語) - 2024年3月28日 (木) 00:17
- ^ 清涼殿にて開催される漢詩の会(中殿作文)と和歌の会(中殿歌会)を合わせて中殿御会という。これは代始めの儀式の一つであり、この儀式を以って以降内裏で開かれる漢詩会・歌会は公宴となる。幼帝の多い中世においては稀であった。 ^ 後光厳朝初。 ^ 柳原忠光は院執権、広橋仲…54キロバイト (8,007 語) - 2024年4月11日 (木) 01:13
- 小槻氏(おつきうじ/おづきうじ)は、「小槻」を氏の名とする氏族。 第11代垂仁天皇の皇子を祖とする皇別氏族で、平安時代から小槻宿禰姓を称した。 平安時代から明治維新まで朝廷に仕えた下級公家の一族である。太政官弁官局における事務官人の家柄として左大史を代々務め、そのほかに算博士・主殿頭といった官職を世襲した。…33キロバイト (4,345 語) - 2024年5月7日 (火) 12:06
- 垂らし彦」の称号があったとは考えがたいとし、以後の時代に大陸思想の影響から芽生えたとみている(また、「天子」という語が反感を受けたのに対し、「天垂らし彦」の反応が低かったことに注目している)。王仲殊も阿毎多利思比孤は「天足彦(天の満ち足りた男子)」とした(天垂…85キロバイト (8,657 語) - 2024年3月3日 (日) 12:57
- 後白河天皇 (二頭政治と法住寺殿造営の節)徳院が同じ御所に住むように仰せられた。あまりに近くで遠慮もあったが、今様が好きでたまらなかったので前と同じように毎夜歌った。鳥羽殿にいた頃は50日ほど歌い明かし、東三条殿では船に乗って人を集めて40日余り、日の出まで毎夜音楽の遊びをした」と自ら記している。 その没頭ぶりは周囲からは常軌を逸したもの…133キロバイト (25,059 語) - 2024年3月21日 (木) 05:30
- 五十鈴依媛皇后 安寧 渟名底仲媛皇后 懿徳 天豊津媛皇后 孝昭 世襲足媛皇后 孝安 押媛皇后 孝霊 細媛皇后 妃倭国香媛 妃絙某弟 春日千千速真若媛 孝元 欝色謎皇后 妃埴安媛 開化 伊香色謎皇后 妃丹波竹野媛 妃姥津媛 鸇媛 崇神 御間城姫皇后 妃遠津年魚眼眼妙媛 妃尾張大海媛 垂仁 狭穂姫皇后 日葉酢媛皇后…92キロバイト (13,441 語) - 2024年4月24日 (水) 09:35
- 江戸時代の社地も現代と同じ規模であるが、当時は石段を上ってすぐの参道西側に佐美長神社末社の「瑞樹社」、佐美長神社の殿地と古殿地の中間付近の東側の位置に「神楽殿」、佐美長御前神社に並立して最東端に佐美長神社末社の「秋津社」、「宿衛所」があった。佐美長神社末社とされた「瑞樹社」・「秋津社」…22キロバイト (3,148 語) - 2023年5月27日 (土) 01:09
- 天皇三年紀や『筑前国風土記』に登場する大浜宿禰、履中天皇即位前紀に見える阿曇浜子、舒明朝に百済へ派遣された阿曇比羅夫、斉明朝・天智朝に活動した阿曇頬垂などがいる。 全国の阿曇部を管掌した伴造として知られる有力氏族で、発祥地については筑前国糟屋郡阿曇郷・志珂郷(現在の福岡市東部)説、淡路島説などがある。…19キロバイト (3,349 語) - 2024年6月1日 (土) 14:41
- 仲々寢さうにもなかつた。眞中に砂を掘つて拵(こしら)へた急製の爐を圍み、火影に赤々と顔を火照(ほて)らせ、それでも外からと、下から沁みこんでくる寒さに外套の襟(えり)を立てて頸を縮めながら、私達は他愛もない雑談に耽つた。その日、私達の教練の教官、萬年少尉殿