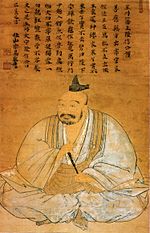検索結果
このウィキでページ「偏城郡」は見つかりませんでした。以下の検索結果も参照してください。
- 茨城県(県庁所在地:茨城郡水戸):常陸国多賀郡、久慈郡、那珂郡、茨城郡、真壁郡 新治県(県庁所在地:新治郡土浦):常陸国鹿島郡、行方郡、新治郡、筑波郡、信太郡、河内郡、下総国海上郡、匝瑳郡、香取郡 印旛県(県庁所在地:葛飾郡加村〈現・流山市〉):下総国結城郡、豊田郡、岡田郡、猿島郡、葛飾郡、相馬郡、印旛郡、埴生郡、千葉郡…175キロバイト (18,809 語) - 2024年4月24日 (水) 12:23
- 常総市 (カテゴリ 結城郡)1954年の市制直前に旧結城郡水海道町となっていた地域 - 「水海道○○町」と表記(○○は水海道市市制施行時に制定された町名)。 1954年の市制直前に旧結城郡水海道町以外となっていた地域 旧北相馬郡坂手村・旧結城郡豊岡村 - 「○○町」と表記(○○は合併直前の村名)。 旧北相馬郡坂手村、旧結城郡豊岡村以外 -…34キロバイト (4,153 語) - 2024年5月22日 (水) 22:34
- 「潞州、下。唐初為潞州、後改上党郡、又仍為潞州。宋改隆徳軍。金復為潞州。元初為隆徳府、行都元帥府事。太宗三年、復為潞州、隷平陽路。至元三年、以渉県割入真定府、以録事司併入上党県。領七県:上党、下。長子、下。屯留、下。至元三年、省入襄垣。十五年復置。襄垣、下。潞城、下。壷関、下。黎城、下。至元二年、併渉県偏城等十三村入焉」…13キロバイト (2,579 語) - 2023年5月25日 (木) 12:40
- 。明治時代以降は納豆(水戸納豆)の生産が盛んになった。 中心部を含む市域の大部分は旧茨城郡(1878年〈明治11年〉より東茨城郡)であり、茨城県の名称は県庁が茨城郡水戸に置かれたことに由来する。市域の一部に旧那珂郡域を含む。 関東平野の東側に位置し、茨城県の県央地域に区分される。…147キロバイト (16,251 語) - 2024年6月4日 (火) 03:41
- 国分氏 (陸奥国) (カテゴリ 宮城郡)南北朝時代に現れる国分氏は前述の藤原北家秀郷流で、国分寺郷を領し、戦国時代には近隣の土豪を従えて宮城郡南部から名取郡まで勢力を伸ばした。居城としては千代城(仙台城の前身)、小泉城(若林城の前身または近接地)、松森城が伝えられる。北で留守氏と対抗し、南で伊達氏に面して和戦があった。…32キロバイト (4,336 語) - 2023年7月22日 (土) 04:10
- びん)は、中国三国時代の蜀漢の武将。本貫は荊州零陵郡泉陵県。 祖先は彭城郡の人だったが、曾祖父の劉綽が零陵太守に任じられ、荊州へ移った。祖父の劉優は孝廉に挙げられ、後漢の献帝の時代に侍御史となり、さらに御史大夫や尚書右僕射へ進んだ。また一族は同じ零陵郡の蔣氏と婚姻を結び、姻戚関係となった。…3キロバイト (510 語) - 2024年5月11日 (土) 16:18
- 城郡の郡治とされた。唐代が成立すると618年(武徳元年)に澮州、翌年には北澮州の州治めとされ、905年(天祐2年)には澮河にちなんで澮川県と改名されている。宋代になると翼城県と改称、金代になると翼州に昇格したが、元代により再び翼城県と改められ現在に至る。 翼城…5キロバイト (490 語) - 2022年10月2日 (日) 16:20
- 榊原政敬(まさたか)従四位下。式部大輔。侍従。 越後国 頸城郡のうち - 614村 刈羽郡のうち - 1村 陸奥国(磐城国) 白河郡のうち - 23村 石川郡のうち - 12村 陸奥国(岩代国) 岩瀬郡のうち - 24村 上記のほか、頸城郡253村の幕府領を預かったが、2村が本藩に、251村が柏崎県(第1次)に編入された。…25キロバイト (3,977 語) - 2024年4月28日 (日) 08:21
- 郡芦屋町、遠賀郡岡垣町、遠賀郡遠賀町、遠賀郡水巻町、春日市、糟屋郡宇美町、糟屋郡粕屋町、糟屋郡篠栗町、糟屋郡志免町、糟屋郡新宮町、糟屋郡須惠町、糟屋郡久山町、嘉穂郡桂川町、鞍手郡鞍手町、鞍手郡小竹町、古賀市、田川郡赤村、田川郡糸田町、田川郡大任町、田川郡川崎町、田川郡香春町、田川郡…90キロバイト (7,700 語) - 2024年5月29日 (水) 11:22
- 三潴県の杵島郡・松浦郡の区域が長崎県に編入 6月21日 - 三潴県の藤津郡の区域が長崎県に編入 8月21日 - 三潴県が廃止され、佐賀郡・小城郡・神埼郡・基肄郡・養父郡・三根郡が長崎県に合併 1883年(明治16年) 5月9日 - 長崎県の10郡(佐賀郡・小城郡・神埼郡・基肄郡・養父郡・三根郡・杵島郡・藤津郡…123キロバイト (14,897 語) - 2024年6月5日 (水) 05:27
- 三根郡 - 11村 佐賀郡のうち - 92村 神埼郡のうち - 39村 養父郡のうち - 10村 小城郡のうち - 22村 杵島郡のうち - 50村 藤津郡のうち - 18村 松浦郡のうち - 36村 彼杵郡のうち - 6村 高来郡のうち - 39村 上記のほか、明治維新後に釧路国釧路郡、川上郡…35キロバイト (4,952 語) - 2024年5月15日 (水) 10:53
- 仙台藩 (防衛ライン・城・要害の節)陸奥国(陸前国)名取郡(61村)、宮城郡(78村)、黒川郡(49村)、加美郡(38村)、玉造郡(21村)、志田郡のうち(43村) : 仙台藩として存続 陸奥国(陸前国)柴田郡(35村)、(磐城国)刈田郡(33村)、伊具郡(36村)、亘理郡(26村)、宇多郡のうち(9村) : 白石藩(旧盛岡藩) 陸奥国(陸前国)牡鹿郡…93キロバイト (13,827 語) - 2024年6月3日 (月) 01:09
- オープンストリートマップに熊本城の地図があります。 熊本城(くまもとじょう)は、熊本県熊本市中央区(肥後国飽田郡熊本)にあった安土桃山時代から江戸時代の日本の城。別名「銀杏城(ぎんなんじょう)」。 加藤清正が中世城郭を取り込み改築した平山城で、加藤氏改易後は幕末まで熊本藩細川家の居城だった。明治時…90キロバイト (15,420 語) - 2024年6月2日 (日) 23:25
- 龍造寺隆信 (家臣・偏諱を受けた人物の節)天正9年(1581年)、龍造寺軍は龍造寺政家を主将として肥後へ侵攻、4月までに山鹿郡の小代親伝、菊池郡の隈部親永、大津山資冬、戸原親運、益城郡の甲斐宗運、合志郡の合志親為、飽田郡の城親賢、隈府の赤星統家、球磨郡の相良義陽が参陣した。また先陣の鍋島信昌は、隈府の赤星親隆、山本郡の内空閑鎮房を下し、肥後計略は完了、龍造寺軍は帰陣した。…29キロバイト (4,751 語) - 2024年2月12日 (月) 06:59
- 浜の館に復させ、それにより地位を確立。敵対勢力を破り、惟豊を阿蘇郡に戻し、以後、その重臣として阿蘇氏を補佐することになった。 天文10年(1541年)、その子甲斐親直(宗運)は、島津氏に内通して阿蘇大宮司に背いた御船房行を益城郡の御船城に攻めて御船城主となり、筆頭家老として軍事外交両面において阿蘇氏…11キロバイト (1,426 語) - 2023年11月14日 (火) 13:43
- と海道平氏との間に緊密な同族的連合が形成された史実に影響を蒙ったからであると推察できる。 『続群書類従』「清原系図」には、清原武衡について、「奥州磐城郡に住す。寛治五年十一月、源義家か為に滅ぼさる」と記されている。また、『百錬抄』寛治元年(1083年)12月26日条には「平武衡」と武衡の名が平姓を冠…11キロバイト (1,746 語) - 2023年11月27日 (月) 09:46
- 鍋島直茂 (家臣団・偏諱を与えた人物の節)天文7年(1538年)、鍋島清房の次男として生まれる。母は龍造寺家純の娘・桃源院。天文10年(1541年)、主君・龍造寺家兼の命令により、小城郡の千葉胤連(西千葉氏)の養子となる。しかし天文14年(1545年)に少弐氏によって龍造寺家純らが殺され、家兼が逃亡したことにより、龍造寺氏と少弐氏が…17キロバイト (2,663 語) - 2024年5月1日 (水) 12:52
- 宣城郡、当塗(とうと)の民に劉成、李暉(りき)の二人があった。かれらは大きい船に魚や蟹のたぐいを積んで、呉(ご)や越(えつ)の地方へ売りに出ていた。 唐の天宝十三年、春三月、かれらは新安から江を渡って丹陽郡にむかい、下査浦(かさほ)というところに着いた。故郷の宣城